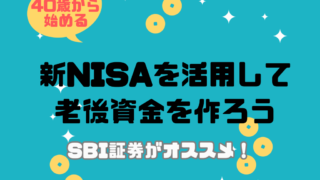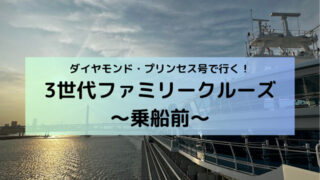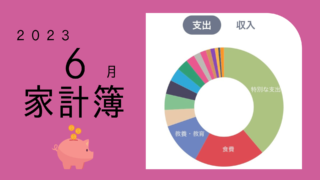コロナ禍以降に入社してきた若手の育成ってホント難しい・・・。
けれど、オフィスワーク時代の 「門前の小僧 習わぬ経を読む」 の成功体験は捨てていく。
そして、新たな働き方・育成の仕方を再設計していくことが自分の進化につながると信じるしかない。
前回、働き方研究の第一人者で、ベストセラー「LIFE SHIFT(ライフ・シフト)」「ワーク・シフト」の著者であるロンドン・ビジネススクールのリンダ・グラットン教授のアーカイブ配信をレポしました。
さらに、ここでの学びもシェアします。
ええーー。
文字情報だけだと、期待値を推し量り、コントロールするの、難しいじゃん。
最終的にやり直しになったら、そっちこそ効率悪すぎるんじゃないかな〜。
って思うののですけども。
グラットン教授のセミナのなかで、仕事の4つの要素、
①集中 ②調整 ③協力 ④エネルギー
という話があったのですが、若手は、①集中 の仕事が中心となっており、
数少ない、②調整 に関しても、教えてほしい、が中心で、「一緒に検討する」と言うステージになっていない状況でした。
①集中(フォーカス)
多くのエネルギーや高いモチベーション、集中力が必要。
何かに一人で取り組む仕事。
ex.執筆②調整(コーディネーション)
他の誰かと時間を調整することが必要。
声を掛け合いフィードバックする、すべきことや今後の計画を一緒に検討する仕事。
ex.リサーチチームと会い、次に何をすべきかを検討する③協力(コラボレーション)
誰かと一緒に創造性を発揮が必要。
自分達の仕事について話し合う、
ex.新製品についてディスカッションする、顧客と面談する④エネルギー
よく生きて成功して食べて運動する。
若手には、「①集中」の業務が多い。
自分はプロジェクトマネジメントが多いので、部門を超えた ②調整、③協力 が必要なためオフィスへ出社する意味もある。
オフィスにいても、周囲とのコミュニケーションが発生しないのであれば、若手にとっては通勤をするのは無駄に感じられるだろう。
その辺りは、若手は周囲に忖度することなく、ドライで合理的だ、と感じている。
では、②調整、③協力 はどうトランスファーしていくべきなのか。
「門前の小僧 習わぬ経を読む」
つまり、上司や先輩の技を盗めるのがオフィスだったのだけども、今はちがう。
「盗め」
と言うように職人芸的に伝えるのは、オールドタイプだと認識して、自分も考えないといけない。
第8回 誰が新人や若手を指導すべきなのか?
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO02856300X20C16A5000000/
ここでは、セミナーなどで若手育成の基本的な進め方を学ぶべきと書かれている。
早いうちにセミナを受ける!!
まずはこれをToDoリストに入れておこう。